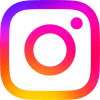お悩み一覧
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎とは、多くはアトピー素因(アレルギー性の喘息および鼻炎、結膜炎、皮膚炎の家族歴や既往歴)を持つ、増悪と寛解を繰り返す痒みの強い湿疹を主症状とする疾患と定義されています。
うまれつき皮膚のバリア機能が低下していることが多く、乾燥している状態とアレルギー体質が原因となって起こります。
アトピー性皮膚炎では湿疹がよくなったり悪くなったりを繰り返し、なかなか治らないことが特徴です。一般的に、湿疹が6ヶ月以上続く状態を慢性と呼びます。(乳幼児では2ヶ月以上続く状態を慢性と呼びます。)

場所は肘の裏側や膝の裏側、首などのこすれやすい場所や、おでこなどの顔面にも出やすいといわれています。
子供の頃にアトピー性皮膚炎と診断されても成人するまでに落ち着いて治ってしまうこともしばしばあります。しかし、中には成人してもなかなかよくならない方も見受けられます。
皮疹の程度、かゆみの強さなどにより、その人にあった治療法を選択していくことが重要です。
アトピー性皮膚炎の原因
- 乾燥肌
- アレルギー体質
- 外からの刺激
など様々な要因が重なってアトピー性皮膚炎を発症すると言われています。
- 乾燥肌:皮膚の大切な役割として、体の水分を保持したり、外からの異物を排除したりするという役割があります。アトピー性皮膚炎の患者様の多くに、皮膚のバリア機能に重要な「フィラグリン遺伝子」の変異があるということがわかっています。フィラグリン遺伝子の異常がある方は、角層の大切な成分である「セラミド」が少なくなってしまうため、皮膚バリア機能が低下し体の水分が逃げやすくなりカサカサとした皮膚となり、外からの刺激にも敏感になります。
- アレルギー体質:体の中に異物が侵入すると、その異物を排除するため、免疫細胞が働きます。アトピー性皮膚炎に関わる有名な物質として「IgE抗体」があります。IgE抗体が多くなると、かゆみを引き起こす「ヒスタミン」や「ロイコトリエン」などの物質が放出されアレルギー反応を起こします。IgE抗体は異物の排除をしようとしてくれますが、アレルギー体質の方は、無害なもの(例えば花粉など)も排除しようとしていまいIgE抗体が多くなり、かゆみが引き起こされます。つまり、様々なアレルゲンに体がさらされることで皮疹の悪化につながります。
- 外からの刺激:アトピー性皮膚炎の患者様は、①で説明したように乾燥肌で外からの攻撃に弱く、外からの刺激が皮膚内部に到達しやすくなっています。例えば汗やよだれ、涙などの生理的なものから、石けんや洗剤などの日用品、ダニやほこりなど様々な刺激により、病気の悪化が起こるとされています。
アトピー性皮膚炎の治療
アトピー性皮膚炎の治療には、保湿剤、外用薬(塗り薬)、内服薬(飲み薬)、紫外線療法、注射などがあります。
外用治療:保湿剤、ステロイド軟膏、タクロリムス軟膏、JAK阻害薬軟膏、PDE4阻害薬軟膏など
詳しくはこちら アトピー性皮膚炎の外用療法について
保湿剤
治療の一番の基本は「保湿」です。
アトピー性皮膚炎の方の皮膚は通常と比べて乾燥しやすく水分が保てないのが特徴です。毎日の保湿を行い、「乾燥しにくい」状態にすることが大切です。
入浴した後の皮膚は潤いが多くなる、と思っている方も多いですが、実際のところ入浴直後は皮膚の表面に水分が付着していますが、蒸発するとともに入浴前よりも乾燥してしまいます。そのため、入浴直後に保湿剤で潤いを保つことが重要です。
保険適応の薬剤で有名なものとしてはヘパリン類似物質があります。
自費診療での化粧品の類いでも保湿に優れているものは多数あり、当院ではサンプルのお渡しもしておりますので気に入ったものを使って頂ければと思います。
外用薬
日本では、炎症をおさえる外用薬が何種類か出ています。
ステロイド外用薬
皮膚の炎症を早期からおさえてくれます。炎症を抑える強さによって5段階にわかれており、炎症の起こっている部位や強さによって皮膚科医が適した強さのものをセレクトして処方します。
ステロイドと聞くと怖いイメージがある、あまり使いたくない、とおっしゃる方もみえます。それは主に副作用を考えてのことだと思います。確かに内服のステロイドは胃潰瘍や感染など、気をつけなければならない副作用が多数ありますが、外用の場合は塗った部分に作用するため吸収はほとんどされません。皮膚に塗ったときのステロイドの副作用としては、皮膚が弱くなる、毛細血管が拡張して赤みを帯びて見える、などがあります。
しかし適した強さのものを適した期間使えば副作用はそこまで心配はありません。中途半端に使うとかえって症状を悪化させたり長引かせたりすることがあるので、指示通りに、必要な量を必要な期間、必要な部位に使い続けることが大切です。
タクロリムス軟膏(プロトピック®)
ステロイドではない機序で免疫抑制をし、炎症を改善する塗り薬です。ステロイドのような皮膚が弱くなったり毛細血管が拡張したりといった副作用は出ないと言われています。強さはストロングクラス(3番目の強さ)のステロイドと同等ぐらいだと言われています。そのため、顔面や首などの皮膚が薄い場所への使用が適しています。
ただ、使い始めにピリピリとした刺激感やほてりを感じることが多い薬剤です。しかしその刺激感は1~2週間すると感じなくなっていくため、少しの間使い続けてみることが重要です。
JAK阻害薬軟膏(コレクチム®)
ステロイドではない機序で皮膚の過剰な免疫反応を抑えることで、皮膚の炎症をしずめて、アトピー性皮膚炎の皮膚症状を改善します。2023年1月より生後6ヶ月から使えるようになりました。強さはステロイドのストロング~ミディアムクラス(3~4番目の強さ)と同等のお薬といわれていますが、効いてくるのに時間がかかり、効果を感じるまで数ヶ月を要することもあります。
ステロイドのような皮膚が薄くなったり毛細血管が拡張したりといった副作用や、プロトピックのような刺激感はありません。ただ、かぶれを起こしたり、ヘルペスができやすくなったりといった副作用が起きうると言われているため、異常を感じた際は早めにご相談ください。
PDE4阻害薬(モイゼルト®)
2022年6月から処方が可能となった外用薬です。ステロイドやタクロリムス、JAK阻害薬とは異なる新しい作用機序を持った安全性の高いお薬です。
タピナロフ(ブイタマー®)
2024年10月から処方が可能となった最新の外用薬です。アトピー性皮膚炎だけではなく乾癬の患者様も使えるのが特徴です。芳香族炭化水素受容体という転写因子を活性化することで炎症を起こす原因となるサイトカインを低下させます。同時に、抗酸化分子の発現も誘導して皮膚の炎症を抑制するとともに皮膚バリア機能を改善します。
内服薬
抗ヒスタミン薬:じんま疹や花粉症に使われる、アレルギーを起こす「ヒスタミン」という物質をブロックするお薬です。かゆみを抑える効果があります。劇的な効果はありませんが、かゆみを少し抑えることによって皮膚をかくことを減らし、皮疹を改善できる可能性があります。
ステロイド:外用薬と抗アレルギー薬で抑えられないほど重症な場合は、ステロイドの飲み薬を一時的に使うことがあります。かゆみを抑える効果が強いです。ただ、血糖値が上がったり胃が弱くなったりとした副作用が出やすいため、使用する期間は短期間にする必要があります。自己中断をすると副作用が出る可能性があるため、内服に関しては診察時の説明に従ってください。
シクロスポリン:ステロイドとは異なる、免疫抑制剤という種類のお薬です。即効性があり、かゆみや皮疹を速やかに抑える効果があります。服用中は、血圧が上昇したり腎臓の機能が低下したりすることがあるので、定期的に採血する必要があり、皮疹が改善した場合は早めに終了することが多いです。
JAK阻害薬:元々関節リウマチなどに使われていたお薬で、近年アトピー性皮膚炎にも適応が通りました。かゆみを抑える効果が非常に強く、難治なアトピー性皮膚炎に最適なお薬です。ただ、免疫の機能を下げるため、ヘルペスや結核などの副作用が出てこないか定期的な採血検査やレントゲン検査が必要であるため、当院での導入は今のところ行っておりません。
紫外線療法:全身の皮疹に紫外線を当てる治療です。かゆみや皮疹自体を改善していく効果があります。その人にあった強さで当てるため、導入した直後は弱い強さから初めて徐々に強くしていきます。そのため効果が感じられるようになるまで時間がかかる場合もありますが、続けていくことで症状が軽快します。
注射
デュピルマブ(デュピクセント®):アトピー性皮膚炎の炎症を引き起こすと言われているサイトカイン「IL-4」「IL-13」をブロックする注射です。炎症を引き起こす原因を止めるので、かゆみや皮疹に対して高い効果が得られます。ただ、一度中止すると次に使ったときに効き目が悪くなることがあるため、中止するタイミングは慎重に相談して決める必要があります。2週間に1度の注射で値段が高い治療となりますが、自分やご家族でうてる方は受診された際に3か月分処方をすることができるため患者様によっては高額療養費制度を用いて補助を受けることもできます。詳しくは受診時にご相談ください。